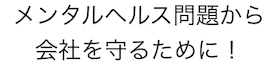心とカラダの基本!よく眠れる3つの習慣

暑い日が続いていますが、眠れていますか?
今年も梅雨明けの8月から、最高気温は体温と近いくらいに上がり
体力が消耗してしまいますね。
こういう時期こそ、しっかりと質の高い睡眠をとりたいところです。
そのために「眠りのメカニズム」と快適な眠りのためにできる3つのことをご紹介していきます。
目次
1、眠りのメカニズム
眠りの仕組みは、大きくわけて2つあります。
1つ目は、「疲れて眠くなる」=ホメオスタシスが働いた結果、体の疲れだけでなく脳が疲れてくると、眠たくなります。それはちょうどパソコンなどでも熱がこもってくるとオーバーヒートしてしまうように、脳の熱がこもると機能が低下してくるような状態です。(*ホメオスタシスというのは、今の現状で維持しようとする機能をさします)
2つ目は、「夜になったから眠くなる」=体内時計が機能しているといえますね。いつもの就寝時刻になると疲れ度合いにかかわらず、「眠くなる」という仕組みです。
ちょうど朝起きて太陽を浴びてから14〜16時間くらい経過すると、眠気がやってきます。この時のポイントが眠くなる時間帯に、体の内部や脳の温度が低下してくる状態を作るということが大事なのです!
起床して太陽光を浴びずに、暗い部屋で昼過ぎまで眠っていると、リズムが崩れ、夜の入眠がうまくいかないということになります。
2、良い眠りのための習慣とは?
何か眠りのために工夫していることはありますか?
研修などでたずねると、日頃気をつけている人からは「眠りの準備」をしている声が聞かれます。一方で悪い習慣をたずねると、誤った情報によるものが多く聞かれます。
①暑い夏は夜中の室温を一定に保つ
室温はどれくらいにキープしていますか?エアコンが苦手という人は、エアコンを付けない、もしくはタイマーで途中で切れてしまうことがあるようです。
朝までぐっすり眠れているなら、問題はないでしょうが、この暑さです、なかなか寝付けない、途中で目が覚めてしまうということがあるかもしれません。
夜になるとメラトニンという物質が松果体から分泌され、手足から体内の熱が放熱されていきます。体の中の温度や脳の温度が低下してくると、徐々に眠気が催されるというメカニズムです。

出典:日経ARIA「睡眠関連ホルモンの1日の分泌リズム」より
このメカニズムから考えると、室温が暑すぎると体内の放熱がうまくいきません。そういう意味ではエアコンの設定温度をやや低めに設定するとよいとされています。
同じ意味で、冬場の冷えについても、手足が冷えすぎていると、放熱という仕組みがうまくいかないため、よく眠れないという理由がわかりますね。
②朝起きたら、しっかりと朝日を浴びる
天気の良い日には、カーテンをあけてしっかりと朝日を浴びてください。
私たちの体内時計はおよそ25時間周期となっており、放っておくと毎日少しずつ就寝時間が遅れることになります。それを朝光を浴びることで、体内時計をリセットすることが必要です。
光の入らない部屋で生活し続けていると、起床時間が毎日1時間ずつ後ろに遅れてしまいます。積極的にカーテンを開けて、光を浴びましょう!
③ブルーマンデーを避けるために
マンデー=Monday というので、土日のお休みを基準にお話しします。シフト制の人は休み明けという捉え方をしてみてください。
平日、忙しく過ごしているとどうしても睡眠不足になりがち。そうするとお休みの日の朝はどう過ごしますか?朝はゆっくりと。二度寝を楽しむ。昼まで寝てる・・・等。
だらだら過ごすのは、なんともいいものです。
が、そのつけは休み明け、そう月曜日にやってくるのです。日曜の夜は、月曜に備えて早く寝ようとするもののうまく寝つけません。そりゃあそうです。普段より、何時間も起きる時間が遅くなったわけですから、眠りが訪れる時間も後ろにずれこんでしまいます。
そのうえ「早く寝ないと」と思っていれば、プレッシャーがかかって、ますます寝つきが悪くなり、翌日の朝、なかなか起きられない。月曜の朝がつらい。。。。ブルーマンデーとなるわけですね。「起床がつらい」状態をリセットするには3日ほどかかると言われていますから、そのことを考えるとやはり日曜朝の過ごし方はとても大切だと言えます。
つまりは、ブルーマンデーをを避けるためには、日曜の朝は、いつも通り、できれば朝寝坊も1時間程度の誤差に収めるのが望ましいです。もっといえば、朝起きた時に、朝日を浴びて、朝食をしっかりと摂る!日中に軽い運動ができれば、夜も早く眠けがやってきます。
休み明けの仕事が苦手な人は、起床時間から調整してみてはどうでしょうか?
ちなみに睡眠不足の人は、昼寝で調整が可能です。昼寝の話はあらためてお伝えします。
④ おまけ 朝早く起きたい時は早く寝るの?
と思いますよね。しかし通常24時に就寝している人が、「今日だけ22時」には眠れません。そのためには③と同じです。早く起きなければならない日の前日の朝、早起きするところから始まります。
早く起きれば、早く眠れる。
「早起き」から始めてみましょう。
3、まとめ
心の健康を損なうと、出てくる症状が「眠れない」です。
これは本当につらいものです。
「寝つきが悪い」「途中で目が覚める」「体は疲れているのに眠れない」「ぐっすり眠った気がしない」
高齢者の「眠れない」は、実は実際には眠っているけれど、目が覚める回数が増えるため、寝ている気がしないだけで、検査をすると、案外睡眠はとれていたりするそうです。
しかしメンタル不調者の眠りについては、眠った気がしないだけでなく、実際の睡眠時間はほとんどなく、脳内の興奮状態が続いているケースが多いようです。
睡眠不足は日常生活にも支障が出てくるため、専門家への相談が大切です。
*うつと睡眠に関する記事は「メンタルヘルス強化の鍵を握る睡眠」の記事でご紹介しています。
睡眠の良いリズムは一朝一夕では作れないものです。できることから一つずつよい習慣を積み重ねていきましょう。
心理カウンセラー 森川 祐子
トライアルセッションのご案内
・外出がままならず、ストレスが大きい。
・仕事のこと、将来のことなど、不安が頭から離れない
・漠然とした不安がぬぐえない
・夜、うまく眠れいない。食欲がなく心配 等
現状、オンラインにてセッションをお受けしています。