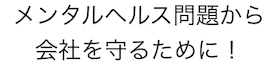冬という季節がメンタルヘルス不調になりやすい理由

最高の組織力を引き出す!
メンタルトレーナーの森川 祐子です。
ご無沙汰してしまいました。秋の研修が一段落したところでようやく「冬編メンタルヘルス」の記事をお届けできます。
この秋は基本的な「メンタルヘルス研修」の次の段階として、それぞれの会社の課題に合わせて行う研修が多かったです。
・復職した人をケアしている社員に、どうケアをすればいいか?「上司の相談力向上研修」
・ストレスの高い職場の若手に対して、ストレス耐性を高める「レジリエンス研修」
・育休や時短を活用している社員への「モチベーション向上研修」等
ニーズは様々です。
このように経営者様、人事労務のご担当者様が抱える問題に対して、事前にヒアリングをさせていただき、オリジナルのコンテンツをご提供させていただいておりますので、お気軽にお問い合わせくださいね。
さて、今年の秋は雨が多く、気温の低い日が多かったですね。朝が早い人は暗いうちに出勤し、真冬のコートを着こんでいるという人も少なくないのではないでしょうか。
今回のテーマは「冬のメンタルヘルス不調」について。実は冬だからこそ、不調になりやすいという理由があります。その要因と解決法について、お伝えいたします。
目次
1、理由その1・・・日照時間
「季節性うつ病」という言葉を聞いたことがありますか?これは、日照時間が大きくかかわっています。
この時期、最も日が短い時期で、昼間の日照時間は10時間程度だと言われています。つまり朝は7時くらいにならないと、夜が明けませんし、夕方も16時を過ぎると暗くなってきますから、早めに出社している人は、太陽の光を浴びる機会が少なくなっているかもしれません。

この日照時間が、”うつ”と関係があります。それは日照時間が短くなることで、うつとかかわりの深い神経伝達物質のセロトニンが少なくなり、身体のバランスにも影響が出ることがわかっているのです。
そのため、毎年冬になると「なんだか調子が悪い」という人は、もしかしたら”季節限定うつ”という可能性が考えられます。
2、理由その2・・・イベント目白押し
理由のもう一つは、年末から年始にかけて、生活のリズムが崩れやすいということです。
12月になると忘年会や、クリスマス、新年会など、行事が目白押し。特に仕事が忙しくて、睡眠時間が短い。疲労がたまっている上に、暴飲暴食が重なると、当然身体への負担が大きくなりますね。
年末年始のイベントも、自分が楽しめているなら、うまくストレス発散になっているでしょうが、我慢して付き合いで参加しているようなら、ストレス要因になっているかも。そこは負担を減らせるように調整してみてくださいね。
身体への負担が大きくなれば、心への影響も少なからずあるものです。
あわせて、寒さへのストレスが増していることも忘れずに。
*多くの人はあまり気づいていませんが、人間にとって「暑さ、寒さ、気圧の変化、騒音等」もストレッサー(ストレス要因)となっているのです。
3、メンタルヘルス不調にならないための3つの方法
「日照時間が短くなること」と、「年末年始といったイベントが多いことによる生活の乱れ」が要因となっているということがわかりましたね。
メンタルヘルス不調になりやすい理由がわかったところで、その対処法を3つご紹介いたします。
3-1、睡眠時間を確保!
この時期は、イベントが続くことで睡眠時間が短くなりがち。寒さのせいで眠りが浅くなり、目が覚めてしまうこともあります。
寒いところにいれば、身体はきゅーっと縮こまって、肩や首がかたくなって緊張しています。その緊張をうまく緩めてやることも質のよい眠りにつながります。
そこでより質の高い睡眠を確保するために、就寝前にしっかりと身体を温めてやることが効果的だと考えます。
あまり寒さを感じにくい人でも、寒さが厳しい日は、芯から冷えているものです。身体が冷えることで免疫低下もありますから、一日一度はしっかりと温めてやることです。
しっかり温めて、しばらくして体温が下がると、自然な眠りが訪れます。

睡眠時間は、忙しい人でも6時間以上は確保したいところですね。もっと言えば、日中高いパフォーマンスを継続して出し続けている人は7.5〜8時間ほどの睡眠を確保していると言われています。
特に冬場は、日照時間が短い=夜の時間が長いので、そのサイクルに合わせる方が身体はラクです。日中の疲労(ストレスや、肉体的疲れ)が大きい人ほど、睡眠時間は長くとることで、身体的、精神的体力を高めることにもつながります。
睡眠はできるならば、起床時間をそろえることがよいとされています。つまり休日も起床時間が遅くせず、昼寝などをすることで調整することが望ましいと考えます。
気になる人は、詳しくは「質の高い眠りを得るための5つの方法」をご覧ください。
3-2、太陽の光を浴びること
朝、起きたときに太陽の光を浴びていますか?
寝室は遮光カーテンなどを使用しているとしても、ベランダなどに出て、起きてすぐに朝日を浴びるといろんな効用があります。

1、冬場は日照時間が短いこともあり、照射量も減りますから、意識的に太陽の光のもとに出ていくことが大切です。それ以外にも、外の空気に触れることで、気分が変わってリフレッシュになるものです。
そもそも日照時間が短くなることで、脳内物質である「セロトニントランスポーター」の働きが変動するために、脳内のセロトニン量が不安定になり、冬季うつが発症しやすくなります。
積極的に朝の時間帯に朝日を浴びて、軽い運動ができればもっといいですね。軽い運動はセロトニンを増やすことにも効果があると言われています。
でも中には、朝早くから夜遅くまで仕事だ!という人もいらっしゃるでしょう。そういう方は、ぜひ職場の照明を明るくしてあげてください。太陽の光には及ばないまでも、同様の効果があると言われています。
そして夜、お休みになるときは、間接照明などオレンジの光に変えてあげることで、目からの刺激を抑えてリラックスすることにもつながります。照明をうまく活用したいですね。
3-3、セロトニンアップを目ざす食事を心がける
日照時間が短くなることで、セロトニン量が少なくなるということがわかりましたね。ではどうやってセロトニンを補ってやったらいいのでしょう?
ズバリ「食事」です。正確に言うとセロトニンの材料である栄養素をしっかりと取り込んでやることです。
ここで、何度も出てきているセロトニンについて補足しておきますね。
3-3-1、セロトニンとは
「セロトニン」とは脳内物質の一つで、人の情緒や睡眠に深く関係のある物質です。別名「幸福のホルモン」とも言われています。そして他の脳内物質とのバランスをとっているため調整系ホルモンでもあります。
脳内でセロトニンが不足することで、寝つきが悪くなる、熟睡できない、朝起きられないといった睡眠に関する不調や、心の安定性を欠くといったものが挙げられます。
脳内物質の一つに「ノルアドレナリン」というものがありますが、これは交感神経を刺激してやる気を高めたり、ストレスに反応して不安や、恐怖、怒りを引き起こすため、別名「怒りのホルモン」などと言われています。
つまり「セロトニン」が減ることで、脳内の「ノルアドレナリン」の濃度が高くなるため、バランスが崩れ、ちょっとしたことで、キレやすくなったり、落ち込みが激しくなったりと、感情面でのコントロールが難しくなります。
こうした側面を見ていくと「セロトニン」がメンタルヘルス不調と、深いつながりがあることがわかりますね。
働く人に多いメンタルヘルス不調”うつ”などは、まさに睡眠障害(眠れない)や抑うつなどといった感情面での不調に苛まれるものです。そのため”うつ”を予防していくためにも、セロトニンを増やすことはとても重要だと言えます。
3-3-2、セロトニンを増やす食事とは
この脳内物質「セロトニン」が心の安定に必要だとわかったところで、「セロトニン」を少しでも増やすためにはその材料が必要です。
その材料こそが食事=栄養素なのです。
特にベースは「プロテイン」つまりタンパク質です。参考までに以下の図をご覧ください。

プロテインを元に、ビタミンやミネラルが反応して、様々な物質が作られていきます。どれかが足りなくても脳内物質は作られません。だからこそ、毎日の食生活でしっかりとバランスのよい栄養を取り続けていくことが大切なのです。当然食いだめ?もできません(笑)
プロテイン=タンパク質を食事で摂るためには、肉・魚・乳製品・大豆製品などをバランス良く摂ることです。女性で多いのは、ダイエットを意識して、植物性タンパク質(大豆等、豆製品)に偏りがちになることです。
もちろん大豆の「イソフラボン」には女性に嬉しい効能があります。それは女性ホルモンと似た働きをするため、更年期の女性にはとても良いとされており、更年期障害特有の症状に対して効果があるとされています。
一方で、タンパク質の体内への吸収率を考えれば、動物性タンパク質の方が高い(これをプロテインスコアといって、スコアが高いほど吸収率が高いと考えます)ので、肉(牛、豚、鶏等)、魚もしっかりと摂りたいところです。
基本的には、食事をベースに考えますが、それでも絶対量を考えれば十分ではありません。ではどれくらいプロテインを撮ればいいのでしょう?
3-3-3、プロテインはどれくらい摂ればいい?
プロテイン摂取量の根拠となる考えは、目安として体重1kgあたり1〜1.5gが必要と考えられているため(分子整合栄養学観点より)、体重50kgの人だと50〜75g必要ということになります。
ちなみに何をどれくらい食べたら、一日の必要量に達するかというと、生卵6.5g/個(たんぱく質量)ですから、1日8〜10個くらい食べるといい・・・?現実的ではありませんね。とにかくしっかり摂らないと足りないということです。
ちなみに牛肉200g食べるとすると、この中に含まれるたんぱく質量は40gとなります。
それにプロテインスコア0. 8(牛肉の場合)をかけて、加熱処理するためさらに半減。
200g → たんぱく質量 40g ×0.8=32g
=32g × 0.5(加熱処理)
=16g

牛肉200g食べても16gですから、かな〜りしっかり摂らないと、足りません。
たんぱく質は、脳内物質の材料であるだけでなく、ホルモン(女性ホルモン等)筋肉、内臓、肌、髪、爪など体を構成するものは、ほぼたんぱく質を材料にしてつくられているため、適切に代謝を行うためにも、たんぱく質は非常に重要な役割を担っているのです。
日頃からセロトニンを意識した食事をしたいものですね。
メンタルヘルスに焦点をあててお伝えしていますが、脳内物質だけでなく、女性ホルモンなども栄養素が大きくかかわっています。妊娠・出産・更年期などを考えると女性にとっては一生通じて、食事はとても大切なものだと言えそうです。また食事の量が多くないという人は、サプリメントなどもうまく活用するといいです。
4、まとめ
いかがでしたでしょうか?
これからますます厳しい寒さが続きますが、元気なメンタルで冬を乗りきるためにも、ぜひ今から出来ることから取り組んでみてください!ここでご紹介したことは特別なことではなく、日常生活を整えていくことが基本です。
しかしながらストレスを多く抱えている人は、人一倍エネルギーの消耗も激しいので、睡眠や栄養面では意識して整えることが大切ですね。
仕事も遊びも、心が元気であってこそ、うまくいくものです。日常生活に心を整える習慣を取り入れてみてください!
メンタルトレーナー
森川 祐子
〜参考記事〜
メンタルヘルスと生活習慣「睡眠」「食事」「運動」の関係でもご紹介しています。
トライアルセッションのご案内
・外出がままならず、ストレスが大きい。
・仕事のこと、将来のことなど、不安が頭から離れない
・漠然とした不安がぬぐえない
・夜、うまく眠れいない。食欲がなく心配 等
現状、オンラインにてセッションをお受けしています。