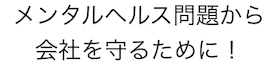パワハラ防止法がスタートしました!準備は大丈夫ですか?

2020年6月より通称パワハラ防止法(正式名称:労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律。略称労働施策総合推進法)がスタートしています。
2019年5月に雇用改正法が改められ、職場におけるパワハラ防止のための雇用管理の措置が義務付けられました。
これまでそれぞれの企業判断に任されていたものが、
法的根拠が生じたことで、外圧としての効力を発揮するようになり、
今後はハラスメント行為が減っていくのではないかと思われます。
しかしそれだけに企業側の責任が問われます。
ただ今回、新型コロナウイルスのことがあり、自宅でのリモートワークへの移行業務の煩雑さや職場に人が集まらないことで、社内的な整備が遅れているという企業もあるかもしれません。
さて今一度、パワハラ防止法の確認とともに、なすべき対策について整理しておきましょう。
目次
1、パワハラ防止法の背景とは
厚生労働省がおこなった「職場のパワーハラスメントに関する実態調査」では、企業の相談窓口で受けた相談の32%がパワハラ関連であったと報告されています。(セクシュアルハラスメントも14.5%)

ハラスメント問題は、日本国内のみならず、世界的にも取り上げられており、「仕事の世界におけるハラスメント」に関する条約案が採択されるよう、日本政府は条約案の支持と採択後の批准を求められています。
国際労働機関(ILO)は仕事の世界における暴力とハラスメントの撤廃に関する条約では以下のように定めています。
【定義】仕事の世界における「暴力とハラスメント」とは単発的か反復的 なものであるかを問わず、身体的、精神的、性的または経済的害悪を与えることを目的とした、またはそのような結果を招く、もしくはその可能性のある一定の許容できない行為および慣行またはその脅威をいい、ジェンダーに基づく暴力とハラスメントを含む。
現状、日本はこうした条約に対しての措置が甘いということを指摘されています。
なぜならセクハラ・マタハラ ・ケアハラに関しては防止措置義務のみで、禁止規定は定められていません。パワハラにいたっては今回ようやく法制化がスタートするとのことで、ようやく一歩前進したというところです。

2、職場におけるパワーハラスメントとは
職場において行われるパワーハラスメントを見てみましょう。
1 優越的な関係を背景とした言動であって
2 業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより
3 労働者の就業環境が害されるもの
であり、1から3までの3つの要素を全て満たすものをいいます。
なお、客観的にみて、業務上必要かつ相当な範囲で行われる適正な業務指示や指導については、職場におけるパワーハラスメントには該当しません。
1)優越的な関係を背景とした言動とは
業務を遂行するに当たって、当該労働者が行為者に対して、抵抗や拒絶することができない可能性が高い関係を背景として行われるものを指します。
例えば、上司と部下という関係性で見れば、上司の指示・命令に対して、部下は「NO」を言いにくいということが考えられます。もちろん一概には言えませんが。
ただ職場という場所では、業務遂行において、ある一定の権限を与えられた上長という立場にある人のパワーが強いということは想像に難くないですね。そういう意味でもパワーのある人は、何もしていなくてもパワーバランスに差があることを認識しなければなりません。
2) 業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの
社会通念に照らし、言動が明らかに会社が求めるところの業務上必要性がない、又はその態様が相当でないものを指します。
しかし、現場で起こる例として、上司として必要だと感じている指示命令(内容や伝え方)が、それを受け取る部下にとって、不適切だと感じる場合もあるでしょう。双方それぞれの言い分があるため判断が難しいケースもあります。
3)労働者の就業環境が害されるもの
当該言動による言動で、就業環境が不快なものとなったため、能力の発揮に重大な悪影響が生じる、見過ごせない程度の支障が生じることをさします。
「不快さ」は人によって、感じ方が異なるため、判断が難しいですね。
しかしながら、「平均的な感じ方」という見方をすれば、大きく外れる判断にはならないように思われます。
また多くのケースは「継続性」という点でも見られますが、その言動の内容によっては「一度」であったとしても就業環境を害する、継続して働き続けることが難しい状況をつくり出すことも考えられます。
3、「パワハラ防止法」法制化にともなう事業者の責務とは
これまでも「パワハラ」対策は多くの企業でも対策してきたことと思います。そのうえで今回、義務化の対象となるのが「大企業」とされており、中小企業にいたっては2022年4月から義務化となるため、それまでは努力義務という扱いです。
まずは自社がどこのカテゴリーに入るかを確認しておきましょう。

これまでは個々の企業努力にとどまっていたところを、一律に組織における責務の範疇を明確にするというのが、この法制化の狙いでしょう。事業主の行うべき3つのポイントをご紹介します。
1)事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発
◯社内で「パワーハラスメントを行ってはならない」ということを、周知徹底することが求められています。
例えば、社内報等で明示する、ポスターによる掲示等、目に付く形で啓発するなどです。
◯行為者について厳正に対処する旨の方針・対処の内容を就業規則等の文書に規定し、労働者に周知・啓発すること
◯ 働く人同士が言動において注意を払うよう研修を実施する等、理解を促す機会を設けること
◯事業主自身(法人の場合はその役員)がハラスメント問題に関する関心と理解を深め、言動に必要な注意を払うこと
→ここで注意したいことは、「就業規則」というものは全従業員が一括りではありません。
雇用形態の違い(正社員・契約社員・パート・アルバイト等)によって就業規則が異なります。
そこで、それぞれの就業規則にハラスメントの項目があるかを確認しておきましょう!
正社員の就業規則にはあるのに、非正規労働者にはないとなると、
軽視しているとの見方をされる場合も。
またうっかり、正社員の就業規則しか作っていなかった!というケースも少なくありませんので
この機会に、雇用形態別に準備しておきましょう。
2)相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
◯「相談窓口をあらかじめ定め、労働者に周知すること」
→「働く人たちが何かあった時に誰に相談していいかわからない」ではまずいですよね。
一般的には社内における相談窓口(人事労務関係部署の人間が、男性担当者/女性担当者として相談対応していることが多いです)があります。
◯社内の人には話しにくいこともあるでしょう。そうした時に活用していただけるのが「社外相談窓口」です。
社内でそうした人材を配置できない小規模事業者においても「社外相談窓口」は有効です。
基本的に、社外においても守秘義務が徹底されているものなので、相談者本人の要望が匿名となれば、秘密は守られます。
→社内において相談窓口を検討されている方は弊社でも承っております。「外部相談窓口」ページをご覧ください。
◯相談窓口担当者が、相談内容や状況に応じ、適切に対応できるように準備しておくことも大切です。
→弊社でも相談窓口対応トレーニングを実施しております。
3)パワハラ事後の迅速かつ適切な対応と再発防止
もし職場でハラスメント行為があった場合、すぐさま対応が求められます。
◯どのような事実関係があったのかを明らかにする(但し、本人同意のもと)
◯パワハラ等を受けた被害者に対する配慮ある対応を行う(部署の異動や、休暇を付与、行為者の謝罪等)
◯事実関係が明らかになった場合は、行為者に対する適切な措置を行う(謝罪、注意、配置転換、減給、懲戒処分等)
_________________________________________________
また相談後、再発防止を含め労働者全体への周知が必要となります。
◯相談者や相談対応した人、行為者、目撃者などの関係者一同がプライバシー保護をするための措置
◯相談者、相談対象者(行為者か不明な段階)が相談、調査を理由に解雇・降格などの不利益な取り扱いをしないように定め、労働者に周知徹底すること。
4、まとめ
パワハラ防止法は、職場でパワハラを起こさないための組織としての取り組みをまとめたものです。
力のある立場の人は、パワハラ行為を行っているという自覚なく相手を傷つける言動をしていたかもしれません。場合によっては意図的であることも。
しかしながら、そうした行為が「うっかり」であろうと「意図的」だろうと、組織の中で起こる問題は、働く人たちのやる気を損ない、生産性を下げ、離職率を高め、労働問題や損害賠償責任にまで発展しうる可能性のあるテーマです。
法制化はあくまで、ハラスメント解決に向けた国としての指針であるため、取り組むべきは、それぞれの組織において、一歩ずつ全社員に浸透させていかなければならないものです。一朝一夕にはいきません。
パワハラ防止法を一つのきっかけとして、働きやすい職場づくりにつなげていってください。
ブルーコンシャス 森川 祐子
参考:東京労働局資料
都道府県労働局 雇用環境・均等部(室)サイト
厚生労働省 都道府県労働局雇用環境・均等部(室)
メンタルヘルスに関することを気軽に聞いてみたい!
・メンタルヘルスケアの問題にどこから手をつけたらいいかわからない!
・メンタルヘルス不調者に対する管理職者の対応について、研修やコンサルタント等について聞いてみたい。
と感じたら、まずはお問い合わせください。