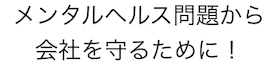労働政策研究機構アンケート結果(全国の労働者10人以上の他業種企業5,250件回答)によると、約6割の事業所でメンタル不全の労働者がいるとしており、うち3割が3年前に比べてメンタル不全者が増加したと答えています。またメンタル不全により過去1年間で1ヶ月以上の休業または、退職した労働者がいる事業場は25.8%となっています。
以上の内容からわかるように、メンタルヘルスの問題は、今や労働問題とは切っても切り離せないテーマになっています。
ストレスの多い環境では、ストレスに耐えることができなくなり、休職による人材の損失や、ストレス症状による生産性の低下、休職、退職者が増える中で残された従業員の負担増による過重労働、企業イメージの悪化、訴訟問題に発展する例もあり、メンタルヘルスは企業成の面からも無視できない経営課題となっています。
弊社での研修ラインナップ
・メンタルヘルス(ラインケア)研修
・メンタルヘルス(セルフケア)研修
・ハラスメント研修(管理者向け)
・ハラスメント研修(一般従業員向け)
・レジリエンス研修
・コーチング研修(管理者・指導者向け)
・メンター研修(管理者・指導者向け)
・アサーティブコミュニケーション研修
・新入社員研修
・内定者研修
・フォローアップ研修
メンタルヘルス(ラインケア)研修/管理者向け
昨今、働く人たちの心の健康=メンタルヘルスに高い関心が集まっています。職場の管理者が部下の抱えるストレスに気づき、対処する方法(ラインケア)を身につけ、「健やかな職場」づくりができるようになることが求められています。

メンタルヘルスへの理解を深めた上で、部下がストレスを抱える要因を把握し、組織として対処するための方法を習得します。
具体的には「ストレスが起こる原因を知る」「ストレスコーピング」「部下のいつもと違う様子に気付くためポイント」「悩んでいる部下への対応の仕方」など事例・ワークを通じて、実践的に部下のメンタルヘルスを考えます。さらに悩ましい問題となりがちな従業員の休職対応や職場復帰支援の仕方も取り上げます。会社と従業員双方にとって安心して働ける組織づくりをめざします。
またメンタルヘルス対策で重要でありながら、一般的なメンタルヘルス研修で取り上げられることの少ない「職場でのコミュニケーション」について、個々のストレスを軽減するのに役立つスムーズなコミュニケーションの取り方も学びます。
組織にとってメンタルヘルス対策の目的は、リスク回避と生産性の向上です。 従業員がストレスを理解し、自分なりのストレス対処法を身につけることで仕事の効率は向上し、利益にも直結します。そのためにも対策は必須であり、職場内ストレスを最小にすることが組織発展のためには重要だと考えます。
研修のお申し込み・お問い合わせ
メンタルヘルス(セルフケア)研修

本研修では、従業員の皆さまがメンタルヘルスについての基本を理解し、自らが抱えるストレスに気付くこと、そしてストレスを解消できるようになることを目的としています。
自己流でうまくいっていることもあるでしょう。けれどストレスの負荷が大きくなった時に自分では対処しきれない事態が起こりうる可能性もあります。そのような時に、注目すべきポイントは何なのか?誰にどのようなポイントで相談したらよいかなど、ご自身や身近な方を守るためにも是非知っておきたいメンタルヘルスの基本について、身につけていただきます。
またあらかじめ、従業員の皆さまのための、ご相談のしくみや相談窓口などもご相談に応じます。
研修のお申し込み・お問い合わせハラスメント研修

平成28年度の民事上の個別労働紛争相談件数のトップはなんと7万件を超える「いじめ・嫌がらせ」でした。この5年間連続トップつまり確実に毎年増え続けています。
ハラスメントは働く人たちの尊厳や人格を傷つける許されない行為であるとともに職場環境を悪化させるものです。この問題は放置されれば、仕事への意欲や自信を失い時には心身の健康や命を危険にさらされることも考えられます。
研修では組織全体でリスクの認識をあらため、一つひとつの行動に自覚をもっていただけるよう伝えていきます。
私どものハラスメント研修では、パワーハラスメント、セクシャルハラスメントを中心に、昨今増えているマタニティハラスメント、アカデミックハラスメント等単なる用語の説明だけでなく事例検討をまじえ、受講者の皆さまにも当事者の立場に立って考えていただくよう行います。
ハラスメント問題は放置しておけば職場環境の悪化やメンタルヘルス問題にも発展しうるテーマであることをあらためて認識する必要があります。
これまでの導入実績
省庁様「管理職向けハラスメント防止研修」/公益財団様「一般職向け/管理職向けハラスメント研修」
都内高等専門学校様「アカデミックハラスメント」/某市町村様「ハラスメント防止研修」
石油関連メーカー様「管理職向けハラスメント研修」/IT会社様「ハラスメント&メンタルヘルス研修」
交通関係協会様「ハラスメント+マタニティハラスメント研修」
ハラスメント研修カリキュラム例
レジリエンス 研修

会社で働く人たちのモチベーションの状態こそが成果に直結します。もしモチベーション向上を妨げているものが
あるとすればその問題を早々に解決していく必要があります。
意外と語られないのが、苦手なことについて。今さら言い出しにくい苦手だと思っているのは自分だけではないか、自分の価値観とは合わないから仕方ない等、相談することもなく、思いこみでうまくいかないケースも少なくありません。
原因をつかみ、思いこみに対する枠組みを変えていく(=リフレーミング)、
苦手なものがもつイメージを変える(=イメージトレーニング)
一人ひとりが肯定感を持つ力を養う(=承認力強化)等
具体的な手法を使って、モチベーションアップにつなげます。
メンタルトレーニング

人の心の状態はいつもモチベーションが高いか?と言われればそういう状態の人はごくわずかだと言わざるを得ません。
ではどうすれば、モチベーションを上げることができるのでしょうか?理想を言えば、都度モチベーションを上げる必要がなく、いつでも叶えたいことに対してモチベーションが高いことが理想です。
「そんなの疲れてしまいそうだ」と言われるかもしれませんが、ここで言うモチベーションは気分や気持ち(感情や気分)ではなく、「やり方」ではなく「あり方」だと思っていただくとわかりやすいかと思います。
そのことがわかれば、『自分が人生をかけて本当にやりたいことは?』『成し遂げたいことは何か?』これがわかると、人生のどこを切ってもあなたの人生はゴールに向かって、モチベーションが高い状態を維持できるのです。
そのためには、本当にやりたいこと、成し遂げたいことは何かを見つけることです。
こういうと「今の仕事でそこまで成し遂げたいことはない」と言う人もいるかもしれません。大事なことは、本質です。
どういう「質」のことに触れていることが、自分にとって大事なのか?今の仕事のなかにはその質は本当にないのか?上辺だけを見てはいないのか?などを明確にして、目標(ゴール)設定をしていきます。
この目標(ゴール)が明確になれば、本来は進むべき方向に人生は進んでいくものです。ただ新しい選択、新しい価値観に触れることで、人は抵抗を感じたり新しいことへの不安を覚えたり、心理的なブレーキがかかるものです。
そこで、具体的な手法としては
・イメージトレーニング
・エモーショナル(感情)コントロール
・呼吸法
・リフレーミング
・目標設定 etc.
メンタルトレーニングを行うことで、本来の自分と向き合い、よりしなやかなメンタリティを作り上げていくことが
大切なのです。一緒にあなたのゴールを見つけていきませんか。
メンタルヘルスに関することを気軽に聞いてみたい!
・メンタルヘルスケアの問題にどこから手をつけたらいいかわからない!
・メンタルヘルス不調者に対する管理職者の対応について、研修やコンサルタント等について聞いてみたい。
と感じたら、まずはお問い合わせください。